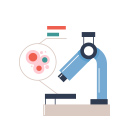HPVワクチン【ヒトパピローマウイルスワクチン(子宮頸(けい)がんワクチン)】
若い女性に増える子宮頸がん
子宮頸(けい)がんは、子宮の入り口(頸部)にできるがんです。日本では年間1万人以上が新たに子宮頸がんと診断され、3000人近くが亡くなっています。近年、若い女性の患者が増えていて、年齢別の患者数は20代後半から増えて40代がピークとなっています。早期発見が可能で、早期に発見されれば比較的治癒しやすいがんとされています。
子宮頸がんのほとんどは、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因です。このウイルスは性的接触で男性にも女性にもうつります。女性の半数以上が一生に一度は感染するとされますが、ほとんどは免疫の力で排除されます。一部の人で感染が長く続き、がんになってしまいます。予防接種によってHPVの感染を防ぐことが子宮頸がんの予防につながります。また早期発見のためにも、定期的な子宮頸がん検診を受けることが大切です。
※病気の詳細はこちら
定期接種は小6~高1相当の女子の希望者に
日本では、HPVの感染を予防するワクチンが2009年12月に販売開始されました。小学校6年から高校1年相当の女子は希望すれば、市町村が費用を負担する「定期接種」で計3回接種を受けられます。ただし、2023年4月から定期接種の対象となった「9価」のワクチンは、1回目の接種年齢が15歳未満の場合に限って計2回(接種間隔は最低5カ月以上とする)の接種でもよい事になっています。
期間外の場合、自分で費用を負担する「任意接種」となります。
厚生労働省は2013年6月からHPVワクチンの積極的勧奨を差し控えていましたが、有効性及び安全性に関する評価、接種後に生じた症状への対応、ワクチンについての情報提供の充実等について継続的に議論が行われ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認されたため、2022年4月から積極的勧奨が再開されています。それに伴い、1997年4月2日~2008年4月1日生まれの女性も、2022年4月~2025年3月の3年間に限定して、公費で接種を受けられました。この期間中に1回以上接種している1997年4月2日~2009年4月1日生まれの方は、2026年3月まで3回の接種を公費で完了できるよう期限が延長されました。
HPVワクチンについては、今後も、安全性の評価、接種後に生じた症状の把握や診療体制強化、地域の支援体制の充実、HPVワクチンについての情報提供の充実などが引き続き行われることが確認されています。
国内には3種類のワクチン
HPVは200以上の種類(型)があり、特に発がん性の高い16型と18型が、子宮頸がん全体の50~70%の原因とされています。国内の定期接種には、この16型と18型などを予防するワクチン3種類が使われています。
この3種類のHPVワクチンは、「VLPワクチン」に分類されます。VLP(Virus Like Particle)は「ウイルス様粒子」、つまりウイルスに似せた粒子のことです。ウイルスを形作る部品であるタンパク質を人工的に作製し、それをもとに作られています。外見はウイルスそっくりですが、中身の遺伝子がなく、注射してもHPVに関連した病気の原因になることはありません。
<HPVワクチンを製造しているメーカー>
・MSD株式会社
・グラクソ・スミスクライン株式会社 (50音順)
ワクチンの有効性は?
定期接種に使われる3種類のワクチンは、16型と18型の感染や、がんになる手前の異常を90%以上予防したと報告されています※1。
HPVワクチンは新しいワクチンなので、時間をかけて発症する子宮頸がんそのものの予防効果はまだ完全には証明されていませんが、子宮頸がんのリスクを約6割低下させるという論文が海外で発表されています。
世界保健機関(WHO)はHPVワクチンの接種を推奨しており、100カ国以上で公的な予防接種が行われています。カナダ、イギリスでは接種率は約8割に達しています。
※1国⽴感染症研究所 9価ヒトパピローマウイルス( HPV )ワクチンファクトシート 令和3(2021)年1⽉31⽇
ワクチン全般における副反応の種類と対策・対応
ワクチンを接種して期待される免疫効果と同時に、接種箇所の赤み、はれ、痛み等の望ましくない局所反応や発熱、リンパ節腫脹等の全身反応を惹起することが多く、これらは“副反応”と呼ばれています。
ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種箇所の赤み、はれ、しこり、発疹などが比較的高い頻度(数%から数十%)で認められます。通常、数日以内に自然に治るので心配の必要はありません。ただし、接種箇所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状がある場合は、医師の診察を受けてください。
ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。このような場合、健康被害を受けた本人やその家族が救済の請求を行うことで、審査が行われ、認定されたときは給付の対象となります。定期接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済の対象となるため、救済の請求は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市区町村に対して行います。一方、任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となるため、救済の請求は独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行います。
ワクチンを接種した後はその場でしばらく様子を見ること、帰宅後もすぐに医師と連絡をとれるようにしておくことが必要です。
HPVワクチンでは広い範囲の痛みや倦怠感、失神など、多様な症状が報告されました。このため、2013年から定期接種の積極的な勧奨は差し控えられていましたが、継続的に議論が行われ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認されたため、 2022年4月から積極的な勧奨が再開されています。
<HPVワクチンで報告された多様な症状>
①知覚に関する症状(頭や腰、関節等の痛み、感覚が鈍い、しびれる、光に関する過敏など)
②運動に関する症状(脱力、歩行困難、不随意運動など)
③自律神経等に関する症状(倦怠感、めまい、睡眠障害、月経異常など)
④認知機能に関する症状(記憶障害、学習意欲の低下、計算障害、集中力の低下など)
参考文献
・厚生労働省ホームページ“ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~”
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html
・国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センターホームページ“子宮頚部”
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/cancer/17_cervix_uteri.html
・新型コロナQ&A:阪大微研のやわらかサイエンス「Q5-2. RNAワクチンとか、不活化ワクチンとか、色々あるけど一体なに?」
http://www.biken.osaka-u.ac.jp/news_topics/detail/1131#Q5-2
・日本ワクチン学会「ワクチン基礎から臨床まで」2018.P215
・日本経済新聞電子版「子宮頸がんワクチン 発症リスク約6割減、スウェーデン」2020年10月19日
・令和3年11月26日健発1126第1号「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000871714.pdf
・一般社団法人日本ワクチン産業協会「2023予防接種に関するQ&A集」
・(公財)予防接種リサーチセンター「予防接種と子どもの健康 2024年度版」から転載(一部改変)
・厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について(2024/5/29閲覧)
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品副作用被害救済制度に関する業務 Q&A (2024/5/29閲覧)
・定期接種実施要領(令和7年3月31日改正)
執筆:2021年9月
最終更新:2025年4月
文責:一般財団法人阪大微生物病研究会
感染症
- 新型コロナウイルス 気になるあれこれ
- 感染ルート 病原体はどうやって運ばれる?
- 予防法・消毒法 正しい予防法・消毒法を解説
- 検査法 どうやって病原体を見つけ出す?
- ウイルスによって起こる病気 ウイルスは体になにをする?
- 細菌によっておこる病気 細菌がひきおこす病気いろいろ
- 寄生虫によって起こる病気 世界3大感染症の一つも実は寄生虫が原因!
- ノーベル賞 感染症の研究成果に贈られたノーベル賞
- 蚊がはこぶ病気