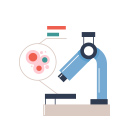おたふくかぜワクチン
おたふくかぜと呼ばれる流行性耳下腺炎
おたふくかぜは流行性耳下腺炎とも呼ばれ、ムンプスウイルスへの感染により耳の下の唾液腺などが腫れます。感染力が強く、3~6歳の患者が全体の約6割を占めています。
髄膜炎や難聴、精巣炎、卵巣炎などを引き起こすことがあります。
小学校入学前に2回の接種を推奨
おたふくかぜワクチンは定期接種の対象ではなく、費用を自分で負担する「任意接種」です。日本小児科学会は、1歳と小学校就学前1年間の2回の接種を推奨しています。
予防効果は80%ほど
おたふくかぜのワクチンは、ウイルスの毒性を弱めて病気を起こさないようにした「生ワクチン」という種類です。ワクチン接種によって、おたふくかぜにかかるリスクを80%程度減らせると報告されています。また、ワクチン接種をしていれば、おたふくかぜにかかっても、接種しなかった場合より症状が軽くなるとされています。
<おたふくかぜワクチンを製造しているメーカー>
・第一三共株式会社
・武田薬品工業株式会社 (50音順)
ワクチン全般における副反応の種類と対策・対応
ワクチンを接種して期待される免疫効果と同時に、接種箇所の赤み、はれ、痛み等の望ましくない局所反応や発熱、リンパ節腫脹等の全身反応を惹起することが多く、これらは“副反応”と呼ばれています。
ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種箇所の赤み、はれ、しこり、発疹などが比較的高い頻度(数%から数十%)で認められます。通常、数日以内に自然に治るので心配の必要はありません。ただし、接種箇所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状がある場合は、医師の診察を受けてください。
ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。このような場合、健康被害を受けた本人やその家族が救済の請求を行うことで、審査が行われ、認定されたときは給付の対象となります。定期接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済の対象となるため、救済の請求は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市区町村に対して行います。一方、任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となるため、救済の請求は独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行います。
ワクチンを接種した後はその場でしばらく様子を見ること、帰宅後もすぐに医師と連絡をとれるようにしておくことが必要です。
参考文献
・国立感染症研究所ホームページ 流行性耳下腺炎(ムンプス、おたふくかぜ)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/529-mumps.html
・公益財団法人予防接種リサーチセンター「予防接種実施者のための予防接種必携 令和5年度(2023)」P36、P110
・一般社団法人日本ワクチン産業協会「2023予防接種に関するQ&A集」2023.p75、p233-234
・(公財)予防接種リサーチセンター「予防接種と子どもの健康 2024年度版」から転載(一部改変)
・厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について(2024/5/29閲覧)
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品副作用被害救済制度に関する業務 Q&A (2024/5/29閲覧)
執筆:2021年9月
最終更新:2024年9月
文責:一般財団法人阪大微生物病研究会
感染症
- 新型コロナウイルス 気になるあれこれ
- 感染ルート 病原体はどうやって運ばれる?
- 予防法・消毒法 正しい予防法・消毒法を解説
- 検査法 どうやって病原体を見つけ出す?
- ウイルスによって起こる病気 ウイルスは体になにをする?
- 細菌によっておこる病気 細菌がひきおこす病気いろいろ
- 寄生虫によって起こる病気 世界3大感染症の一つも実は寄生虫が原因!
- ノーベル賞 感染症の研究成果に贈られたノーベル賞
- 蚊がはこぶ病気