希少な血液がんの治療薬開発~臨床と基礎研究が手を組み推進
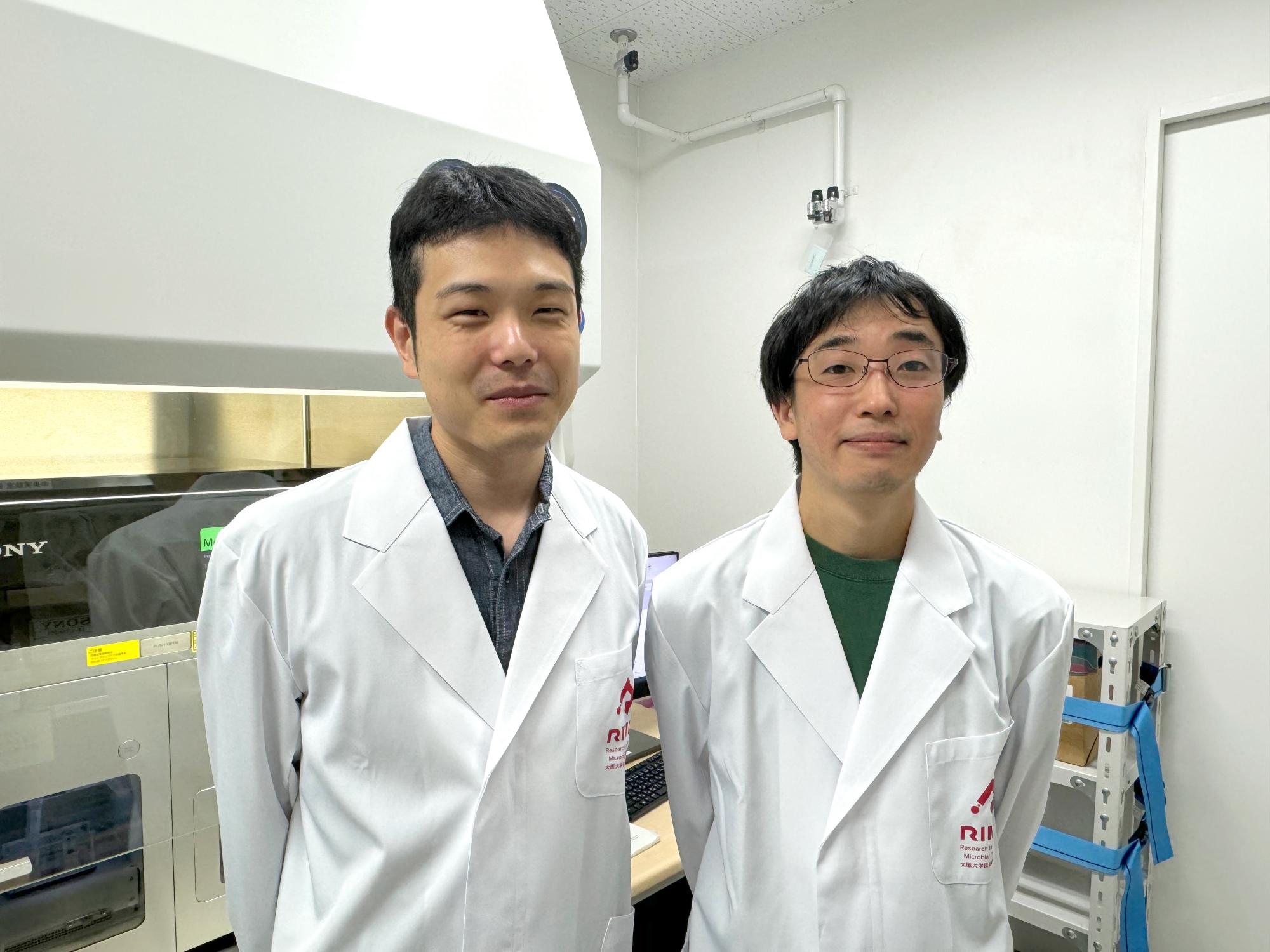
希少な血液がんの治療薬開発~臨床と基礎研究が手を組み推進
診断からの平均生存期間が2カ月足らずの血液がん「アグレッシブNK細胞白血病」(ANKL)。この希少な血液がんの患者が東海大学病院に運ばれてきたことがきっかけで、幸谷愛教授率いる研究室の取り組みが始まりました。その後、治療薬の治験がスタートし、今年から研究室を大阪大学微生物病研究所に移してさらに研究が進められています。ANKLの研究をリードする基礎研究者の宮竹佑治助教と、臨床医の経験がある栁谷稜特任助教の2人に、研究内容を聞きました。
【研究の経緯】
・幸谷教授や宮竹助教、栁谷特任助教らが東海大学に在籍時、アグレッシブNK細胞白血病(ANKL)が肝臓で増殖するメカニズムを解明し、新たな治療法の開発につながる抗体(PPMX-T003)を発見。2023年に論文がBlood誌に掲載される。
・東海大学医学部附属病院で2023年度から、抗体薬の治験がスタート。
・2024年、幸谷教授らが大阪大学微生物病研究所に移籍。
・同年6月にLeukemia誌に掲載された論文で、抗体ががん細胞に対する治療効果を示すには、がん細胞の周りに豊富なアミノ酸が必要であることを報告。抗体が作用するメカニズムの一端を解明した。
<論文>
掲載誌:2023年7月27日付「Blood」
タイトル:The hepatic niche leads to aggressive natural killer cell leukemia proliferation through the transferrin-transferrin receptor 1 axis
掲載誌:2024年6月24日付「Leukemia」
タイトル:Amino acid influx via LAT1 regulates iron demand and sensitivity to PPMX-T003 of aggressive natural killer cell leukemia
――アグレッシブNK細胞白血病(ANKL)の研究を始めたきっかけを教えてください。
宮竹 6~7年前だったと思います。幸谷教授が東海大学で血液腫瘍内科の教授を務めていた頃、東海大学病院に原因不明で症状の悪い患者さんが運ばれてきました。調べたところ、アグレッシブNK細胞白血病という非常にまれな疾患だと分かりました。
アグレッシブNK細胞白血病(ANKL) 希少な血液がん。ナチュラルキラー(NK)細胞と呼ばれる免疫細胞ががん化して発症する。東アジアの若年に多く、診断からの平均生存期間は2カ月未満。患者数が少ないため治療法の開発は進んでいなかった。
宮竹 病気の説明を受けた患者さんは「自分はもう助からなくてもいいから、次の人につなげてほしい」とおっしゃって、研究のために自身のがん細胞を提供してくださいました。
そのがん細胞をマウスの体内で増殖させたところから、私たちの研究は始まっています。
――この疾患の平均生存期間がわずか2カ月未満なのはなぜでしょうか。
宮竹 医師出身の栁谷さんが詳しいです。
栁谷 まれな病気のため診断が難しいうえに進行がとても速く、治療が間に合わなくなってしまうのが一番の理由です。
治療でも難点が生じます。抗がん剤は肝臓に副作用が出てしまうことが多いのですが、ANKLという病気は肝臓を壊してしまうんです。副作用が怖くて抗がん剤を思い切って使えません。
きちんと抗がん剤治療を始められて、その後の移植治療に移れた場合、他のリンパ腫と同程度に高い治療成績を出せることもあります。
――研究はどのように進めたのですか?
宮竹 がん細胞の提供を受けた約1年後、血液専門医の亀田和明さんが大学院生として研究室のメンバーに加わり、私とともにANKLの研究に取り組むことになりました。
私は医師出身ではなく、細胞生物学の分野で基礎研究をしてきた研究者です。新たに何かを発見することには強いのですが、治療に生かす方向に持っていくのは不慣れでした。亀田さんによって、研究に臨床の視点が持ち込まれた形です。
研究で最初に、がん細胞が主に肝臓で増えることが分かりました。ANKLはリンパ球の一種のNK細胞ががん化したものですから、リンパ球が多く存在する脾臓で増えると考えるのが自然です。ところが、脾臓では少ししか増えません。
そこで、なぜ脾臓ではなく肝臓で増えるのかを調べることにしました。肝臓で増える理由を突き止めれば、病気の進行を食い止める治療法の開発につながります。
肝臓と脾臓で増えているがん細胞それぞれについて、遺伝子の発現の違いを網羅的に調べたところ、予想に反して違いはほとんどありませんでした。
そこで、がん細胞自体の違いではなく、周りの環境(微小環境)の違いが影響している可能性を検討しました。肝臓の細胞と何らかの物質をやりとりして、がん細胞が増殖しているのではないかと考えたのです。
――謎解きですね。何が分かりましたか?
宮竹 肝臓と脾臓のそれぞれの細胞で発現している遺伝子を調べる実験などを行った結果、微小環境の違いとしていくつかのタンパク質が候補に挙がりました。その中の一つがトランスフェリンです。
トランスフェリン 主に肝臓で合成されるタンパク質。細胞の増殖などに必要とされる鉄と結合し、体内のあらゆる細胞に鉄を運ぶ役割を果たす。受け取る細胞の表面には「トランスフェリン受容体」があり、この受容体にトランスフェリンが結合して鉄と一緒に細胞内に取り込まれる。
肝臓ではトランスフェリンが多く作られます。肝臓内のがん細胞は、細胞表面のトランスフェリン受容体で鉄を受け取り、増殖に利用するのだと考えられます。エネルギーを作り出すミトコンドリアの機能には鉄が必要ですので、話は合います。
がん細胞のトランスフェリン受容体遺伝子を壊したところ、他の候補遺伝子と比べて最も増殖が抑えられました。このため、トランスフェリン受容体を治療のターゲットにすることにしました。
トランスフェリン受容体をターゲットにしたことには、もう一つ大きな理由があります。バイオベンチャーの「ペルセウスプロテオミクス」が既に、他の病気に対する薬の候補としてトランスフェリン受容体の機能を阻害する抗体「PPMX-T003」の治療開発を進めていたんです。既に抗体があるのですから、阻害剤を探したり、新たに抗体を作ったりしなくて済みます。すぐにペルセウスプロテオミクス社に共同研究を打診しました。
栁谷 トランスフェリン受容体の研究は、2020年春に大学院生として研究室に来た私が担当しました。ちょうど、ペルセウスプロテオミクス社に抗体を提供してもらって、実験をいつでも始められる状態でした。
試しにANKLのがん細胞を移植したマウスに抗体を打ったところ、ものすごくよく効きました。いきなりゴールが見つかったんです。後は、「なぜ効いているのか」を2年かけて探しました。答えを見てから解き方を考えたような感じです。
――薬として期待できますね。
栁谷 ただ、肝臓内のがん細胞には効くのに、脾臓に浸潤するとほとんど効かなくなります。脾臓は生きるために大事な臓器というわけではないため、がんが増殖して機能不全になってもマウスはすぐには死にません。抗体の効果が切れると、がん細胞が肝臓に戻って増殖し、マウスは死んでしまいます。
このため、ANKLの新たな治療法として、この抗体薬を最初に使って肝臓からがん細胞がなくなったところで、従来の抗がん剤を使うという方法が考えられます。治療の問題点だった「診断がついても肝臓が弱っているせいで抗がん剤治療ができない」ことを解決できる可能性が見いだせたことになります。
抗がん剤 正常な細胞とがん細胞の区別なく、増殖している細胞にダメージを与える。肝臓はダメージを受けると細胞が増殖して回復するため、抗がん剤の影響を受けてしまう。
ここまでの研究成果をまとめたのが、科学誌Bloodに掲載された論文です。論文を出した直後にANKLの患者さんを対象とした治験が始まりました。既に実施されていた健康なボランティアの人に投与したデータによると、肝臓にダメージは与えないようです。
私たちは、抗体薬でがん細胞をやっつけた後に健康な人の血液細胞を移植し、そこに含まれる免疫細胞の力で残りのがん細胞をやっつけてもらう治療につなげることを考えています。
――Bloodの論文の後は、どのような研究をしたのですか。
栁谷 Bloodの論文の時点では、「抗体PPMX-T003はなぜ肝臓だけでしか効かないのか」という疑問が解決できていませんでした。まず考えたのは、効かないがん細胞には一部の遺伝子の機能が変わるなどの変化が起きている、という可能性です。
ところが、マウスに抗体を投与した後に残ったがん細胞の遺伝子変異などを調べてみても、大きな変化は見つかりませんでした。そこで、がん細胞の周りの環境の違いが影響し、薬が効かなくなるではないかと考えました。
マウスの脾臓は主に血を作る場所です。脾臓にあるがん細胞の周りは、血液細胞がほとんどを占めます。一方、肝臓は栄養や代謝をつかさどる臓器です。がん細胞の周りには小腸などで吸収された糖やアミノ酸、脂肪がものすごく豊富にあります。
がん細胞は盛んに増殖していますから、栄養がものすごく大事です。がん細胞の周りに栄養があるかないかが薬の効果を決めている可能性を考えて、二つ目の論文の仕事を始めました。
――実施した実験について教えてください。
栁谷 がん細胞をバラバラにして、一つの細胞がどんな遺伝子をどれくらいの量発現しているかを見ました。シングルセルRNAシークエンスという技術です。治療前と治療後のがん細胞、そして肝臓と脾臓のがん細胞を解析すると、脾臓内で生き残ったがん細胞は、わずかではありますが三大栄養素の吸収効率が悪かったんです。特にアミノ酸が顕著でした。
実験を重ねた結果、システインとメチオニンの取り込みが良い細胞ほど抗体の効きが良いことが分かりました。さらに、アミノ酸を細胞内に取り込むLAT1(ラットワン)というタンパク質が機能しないようにしたがん細胞をマウスに移植すると、肝臓内であっても抗体の効きが悪くなりました。
抗体ががん細胞をやっつけるためには、がん細胞がアミノ酸をたくさん取り込むという条件が必要なのだと分かりました。これが2本目の論文の主旨になります。
――この成果は、どのような応用が考えられますか?
栁谷 この抗体薬の後にどの抗がん剤を使えばいいかを検証するための材料になります。抗体薬が効くメカニズムが分かっていないと、抗体薬の効きを邪魔する抗がん剤を併用してしまうリスクがあるからです。
例えば、ANKLは今、抗がん剤で治療していますが、アミノ酸の取り込みを阻害する抗がん剤が一番効くと言われています。そのため、真っ先にその抗がん剤との組み合わせが頭に浮かびますが、私たちの研究成果によると、その組み合わせではダメだということになります。
また、私たちは、がん細胞がどの臓器にあるかによって抗体薬の効きがものすごく変わることを示しました。
これまで、「抗がん剤が効かなくなるのはがん細胞の性質が変わったため」と結論づけられることが多く、がんの「微小環境」も重要だと指摘する人はほとんどいませんでした。今回、微小環境の重要性を指摘できて、学術的にも意味があったと思います。
――研究をしていて、面白さややりがいを感じたのはどういう時ですか?
宮竹 今回の研究は、患者さんにがん細胞を提供していただいたところから始まり、病気の謎を解いていきました。「研究を速く進めることで治療につながり、人のためになる」と常に感じて、やりがいになっていました。
それまでは、ある一つの分子(タンパク質)に注目し、たくさんの実験をして、「この分子はこれに効きます」という発表をすることが多かったんです。今回は目標が明確に決まっていて、「そこに到達するにはどの道を行けばいいんだろう」と探していく感じでした。そこに面白さを感じました。
栁谷 私は、ANKLに対して特別な思いを持っていました。医師になり、山形大学医学部附属病院の血液内科で初めて診た患者さんがこの疾患だったんです。その方は学生時代にお世話になった先生でした。
疾患についての知識が全くなく、経験ゼロからのスタートでした。わだかまりとなって残っていた状況で、たまたま行った先の研究室がこの疾患を研究していた。運命を感じましたね。論文を出して、気持ちの整理を付けることができました。
また、病院の医師から研究室の研究者という立場に変わり、物事をじっくり考えることに楽しさを感じています。
臨床の現場では、検査データを見て、次にどうするかをすぐに判断します。ガイドラインなどで決められた方法に従って、事故が起きないように副作用の管理をしながら患者さんを診ます。立ち止まって一つひとつ考える時間はほとんどありません。
研究者の今は、じっくりと考えることができます。すると、当たり前だと思っていたことが実は当たり前ではなくて、よく考えたら「おかしくないか」っていうことがあることに気付きました。
例えば、どこにがん細胞があっても同じ抗がん剤を使うというのは、よく考えれば理にかなっていません。抗がん剤は全ての臓器に均等に届くわけではなく、届きやすい臓器や届かない臓器もあります。この点をもっと考えて治療すべきではないかと思います。
外の世界を経験して、いろいろと見えてきました。
――お話をうかがっていて、臨床を知る人と基礎研究を続けてきた人がチームを組むメリットは大きいのだと感じました。
宮竹 臨床経験のある人は病気に対する知識が豊富です。一方、私たち基礎の研究者は実験の経験が豊富です。両者がうまくかみ合い、今回の結果につながったのだと思います。
栁谷 臨床の現場にいると、何が問題になっているかが分かります。その問題の解決を目指せば良い研究ができるのですが、臨床医には「どうやって解決すればいいか」のアイデアが全くありません。実験のやり方を研究室で一から教えてもらい、成長させていただきました。
研究室に来て気付いたのですが、私と基礎の研究者とでは興味の方向性が違います。試験管内で何か新しい現象を見つけると、私は「生体内でも同じことが起きるのか」を見たくなります。一方、基礎の方々は、「なぜそういう現象が起きるのか」というメカニズムにすごく興味を持ちます。方向が正反対です。
時にぶつかることはありましたが、どちらの方向性も大事です。研究室に両方のタイプの人がいるということは、どちらの方向にも業績を出せるということ。楽しいですね。
――研究は今後、どのように展開していくのでしょう。
栁谷 この抗体薬自体はANKLだけでなくさまざまな血液がんにも効果がある可能性があります。そちらの方向に広げていきたいと考えています。
ANKLの基礎研究としては、抗体が脾臓や骨髄でなぜ効かないのか、というデータは集まったので、次は「脾臓や骨髄で効くようにするには薬のターゲットを何にすればいいのか」という解析を進めていきたいと思っています。
宮竹 微小環境の差は他のがんでも見られて、それが重要なのではないかという視点で研究を進めています。結果も出てきているので、従来の固定観念を崩せたらいいなと考えています。
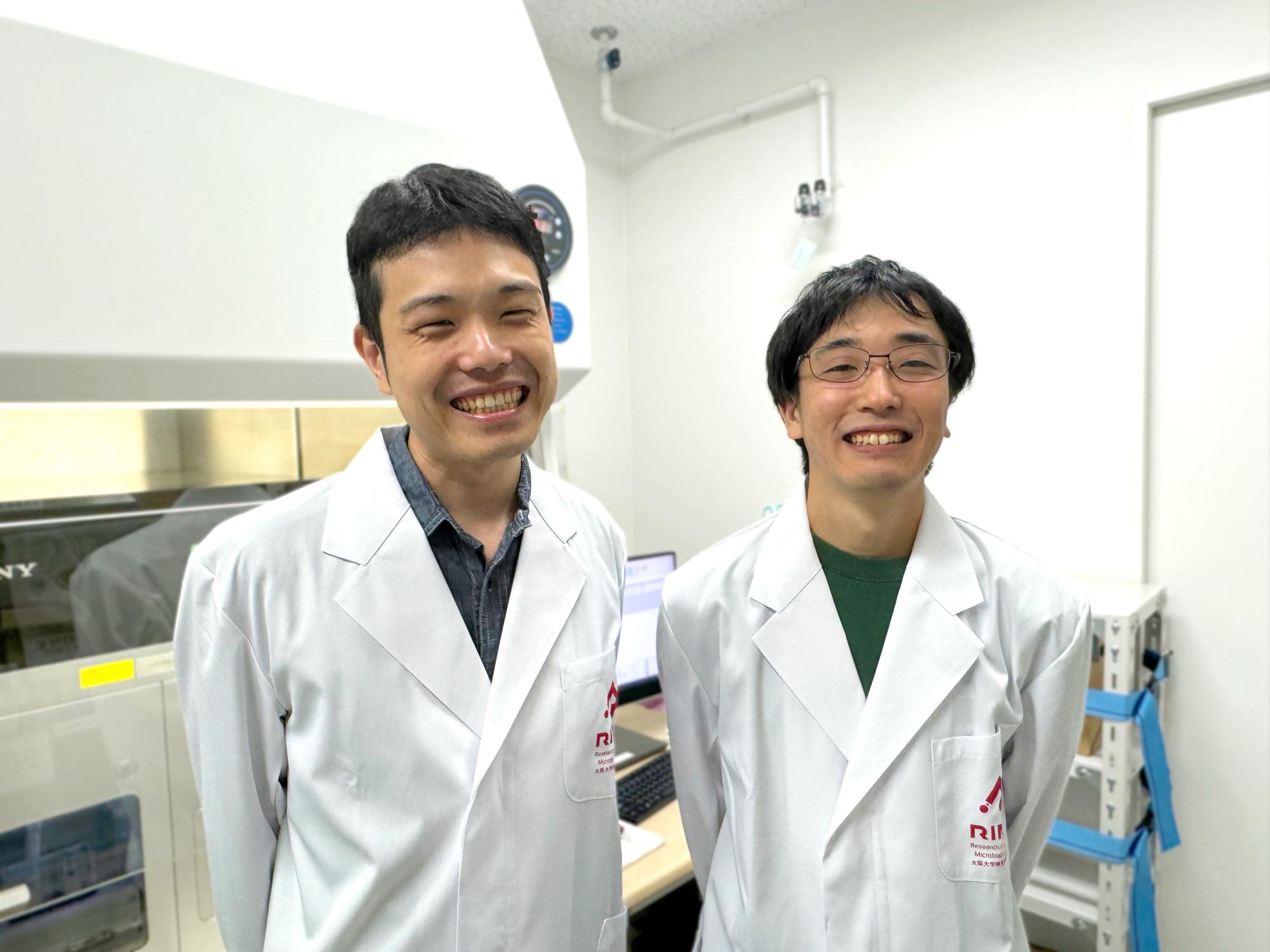
左:宮竹佑治助教、右:栁谷稜特任助教
インタビュー:2024.8月
聞き手:サイエンスライター・根本毅